今回の記事は、マルニ木工のtako(タコ)アームチェアにスポットを当てた内容になっています。記事を書いた時点でのtakoはまだインテリア好きの一部の人が知るという知名度なのではないでしょうか。
しかし、私はこの椅子を
今後世に残る「名作」になる
と確信しています。
デザインされてから数年しか経過していないまだ新しい椅子ですが、私の考えるtakoアームチェアの魅力を余すところなく書いていますので、かなりの長文になると思います。
しかし、takoをご検討されている方にとって背中を押させていただける役立つヒントになればと思っていますので、どうか最後までご覧ください。
takoの伝えたい魅力がたくさんあるため、3つの項目にまとめました。
- takoの「見る」魅力
- takoの「使う」魅力を考察
- takoの「語る」魅力
記事を書いている私自身も、takoを購入し既に3年ほど使用しています。キズやへこみも付いてしまいましたが、どんどん愛着が湧いています。一生使うつもりで購入したものなので、これからどんな変化をしていくか楽しみです。
takoの「見る」魅力
彫刻なのか椅子なのか
タコはどんな椅子か。もし、私が一言で説明するならば
彫刻作品のような椅子
と表現します。
彫刻とは本来、芸術品です。鑑賞するための対象であり、道具としては使わないものを指します。しかし、私はtakoに、オブジェであるかのような美しさを感じます。
家具というよりも、まるで建築の一部であるような魅力
を感じるのです。

デザイナーである深澤直人さんはtakoについて「木が枝分かれしたようなデザインで椅子をつくりたい」と語り、まるで自然の中にあるようなかたちをデザインに落とし込みました。
緩やかにカーブしている脚は、人の体重を支えられるのか?と疑問に思ってしまうくらい華奢に見えます。しかし実際に座ってみると、しっかりと地に着いた安心感があります。

堅い木材で作られているのに、まるで柔らかいような見た目の佇まい。このアンバランス感が、椅子としての存在感をいい意味で曖昧に感じさせ、彫刻的に見せる要因なのでしょう。
道具として誕生したはずの椅子が、道具を超えて建築の一部のような存在感になっていく…というか。takoは椅子としての存在感が良い意味で希薄なんです。
ある意味、椅子っぽくない。(もちろん椅子なんですが)

だから、椅子を置くというよりも
ひとつのアートピースを置いたように見える
んです。
華美な造形美ではなく、引き算を用いたマイナスの美学のように。でも、埋没するわけでもない。本当に素晴らしいデザインです。
自然と人工物の中間
ちょっと話は脱線しますが、私はソロキャンプが趣味で月に1~2回ほどはソロキャンプへ出かけています。キャンプをする中で、ある時ハッとした出来事がありました。
本当に当たり前のことなんですが、それは
直線的なものは人工物にしかない
と、気が付いたこと。
キャンプ中、周りは自然ばかりです。森の中や川べりでキャンプしたこともありますが、完全に真っすぐなものは自然の中にはありません。
草も木も真っすぐに伸びているわけではなく、日の光を求めて左右にうねりながら成長しています。

つまり、自然界に直線はほとんど存在しないんです。
真っすぐなものは人が作ったものだけ。だからこそ人は丸みのあるものに惹かれ、自然から生まれたような曲線に安心感を持つのかも知れません。
工業製品ではないけれど、自然のようなたたずまいで存在する置き物、みたいな。空間に調和し、だけど存在感があるモノ。
彫刻やオブジェはこの
「自然と人工のあいだ」なんじゃないか?
って思うんです。そして、takoも。
takoはそのほとんどが曲線で構成されています。背座と脚、すべてが有機的で直線的な要素がありません。

特に後ろ脚の曲線形状が非常に美しいと私は思います。
テーブルクロスがなだらかな曲線を描いて地面に落ちるような、フワッと優雅に接地している様はフランスのクラシック家具にみられる、猫脚のようです。
脇役だけど重要なパーツ
さらに、takoにとって欠かせない重要なパーツがあります。それは、背とアーム、脚をつないでいる小さなパーツ。このパーツが3つの部材をつなぎ、優雅に調和させています。
小さくともとっても重要なパーツであり、takoの美しさを表現するための名脇役となっています。

takoのデザインが彫刻的でありながら強度も保つことができるのは、このパーツがあってこそ。
まさにこれこそが
機能と美の集成
です。
フラットすぎる継ぎ目
takoの木材同士の継ぎ目をよく見てください。継ぎ目と言うのは、木材と木材のつながりの部分。この継ぎ目がシームレスで、凹凸がありません。滑らかです。
これ、かんたんに見えますがすごく技術のいることなんです。これはマルニ木工にとっての挑戦だったんだろうな、と私は感じます。

こういった難易度の高い加工をするのは、メーカーにとってある種のギャンブルです。
品質が良いものを作り出すことができれば、その技術力を対外にアピールするチャンスになりますが、逆に作りが悪いものを世に出してしまうと、メーカーのレベル自体を疑われてしまうんですよね。

フラットにつないだ木部がズレて凹凸ができてしまったら、下手な加工だなって思われてしまう。…言わば諸刃の剣。
だからこそ、こういうところでは初めから勝負しないメーカーが多いんです。敢えてデザインしたようにズラし「ここをずらしてるのは意図的なデザインなんですよ」的な雰囲気を作るように。
言い方が悪いですが、キレイに誤魔化す、んです。しかし、マルニ木工は敢えてこの加工に挑戦しました。木工を生業とするメーカーのプライドなのでしょう。
難易度の高い加工を成功させるため、懸命に努力した結果
であると言えます。
技術が優れている証でもあり、その気概は本当に素晴らしい。
手間もコストもかかる「削り出し」
takoは「削り出し」という技法で作られています。削り出しとは木の塊から削り出して成形することです。
通常、こういった曲線部分には「曲木(まげき)」という技法が使われることが多いです。曲木は木材を熱し圧力を加えながら曲げていく方法です。
曲木は大量生産に向き材料費が少なくて済むため、工業製品などの大量に作るものに向いています。しかしその反面、複雑な形状を表現することができません。
家具で例えると、CH24(Yチェア)の背もたれは曲木です。

Yチェアの背もたれは複雑そうに見えて、実は曲木で作りやすい2次元の曲線です。だから曲木(まげき)で作りやすい。対して、takoは3次元に曲がっています。
作成難易度が高いため、takoは削り出しで作成せざるを得なかったのだと私は思います。削り出しは手間がかかる上、材料を多く使うため価格が高くなりがちです。
しかし、削り出しということを妥協しなった。つまりtakoは、
生産性やコストよりも製品としての理想的な完成像を実現したかった
のでしょう。
だからこそ、唯一無二の形を作ることができたのです。
デザインをした深澤直人さんは非常に珍しいデザイナーで、事前にメーカーの工場へ訪問し「どんなことができるメーカーなのか」というのをしっかりと自身の目で見極めてからデザインを起こすそうです。

多くの工業デザイナーは、デザインを起こしてから実現ができるメーカーを探しますが、深澤さんは「このメーカーは、どんなことが得意なのか」をしっかりと見据えてデザインを起こします。
だからこそ、デザインだけでなく機能とも調和した、優れた製品が生まれるのです。
TAKOを「使う」魅力を考察
握れるアームが良い
チェアにとってのひじ掛け(アーム)は通常、肘を置くためにあります。
タコの場合も腕を置けなくはないですが、アームが細く有機的にカーブしているので、ドカっと腕を置くというよりちょっと乗せるような感覚が近いですね。
しかし、これはデメリットではありません。アームの前方が下がっていて低い位置にあるからこそ、アームをぎゅっと握りやすいのです。
●アームを握っている画像

これがとても良い。
ワークチェア(仕事用の椅子)の場合は、アームに腕を置いたままパソコンのタイピングなどをする用途がありますが、ダイニングチェアは団らんや休息に使うため、肘を置けなくてもそこまでデメリットではありません。
ゆっくりとダイニングで食事をして、談笑しながらアームを握ったり撫でたりするのはとても心地が良い時間です。
映画やテレビを観ながら思い思いのくつろぎ方ができますので、ダイニングで休息をするにはとても適したアームの形状です。
長時間座れる座面のかたち
takoの座面は三次元カーブを描いており、人間の体に合わせたオーガニックな曲面構造です。
takoの前身である、HIROSHIMAアームチェアの座面をリデザインしたのではないかと思いますが、より一層座り心地が良くなっています。

前面は下がり、ちょっと上がって中央に向けてまた下がり、お尻のほうに行くにつれてまた座面が上がります。
彫刻的なフォルムを守りながら、お尻がすっぽりと包まれるような座り心地も兼ね備えています。非常に細かな部分ではありますが、丁寧にデザインが起こされているのを感じます。

座面自体は薄くなり、総合的な重量もHIROSHIMAよりも軽くなっています。
座り心地を落とさず、デザイン性を高める。デザインも使い勝手も決して妥協しなかった、デザイナーとメーカーの執念のようなものを感じます。
HIROSHIMAのリ・デザインと書きましたが、マルニ木工ではHIROSHIMAを「もっと軽くしたい」という狙いもあったようです。
HIROSHIMAアームチェアの重量は8.5㎏、対してTAKOは7㎏と軽量化されています。(木の種類によって違いはあります)
ウレタンなどのクッションがない木の椅子は、座面の形状で座り心地が左右されます。人の身体に密接にかかわる部分だからこそ、マルニ木工は手を抜かずに丁寧なモノづくりをしています。
日々姿を変える椅子
takoは、材料のほとんどが天然木です。天然木は日々使っていく中で徐々に風合いや色の変化が起こります。
ウォールナットの場合は、明るめの茶色に変化していきます。オークの場合は徐々に色が濃くなり、濃いブラウンへと変わっていきます。俗にいう「経年変化(けいねんへんか)」ですね。

機能が上がっていくわけではありませんが、使うにつれて少しずつ姿が変わる様子を見るのは楽しいです。変化が程よいアジとなって、より一層愛着が増すはず。
変わらない無機物も魅力的ですが、ずっと長く使いたい、と決めているものは天然のものである木材や革を使うのがおすすめです。
takoの「知る」魅力
マルニ木工はG7サミットの椅子をつくったメーカー
マルニと聞くとイタリアのファッションブランドの「MARNI」を想像される方もいらっしゃると思いますが、ファッションブランドではなく、日本の家具メーカーである『マルニ木工』のことです。
マルニ木工はもうすぐ創業100年になろうかとしている、日本国内でも最古参の老舗家具メーカーです。
ここで、マルニ木工の果たした大きな仕事を紹介させてください。マルニ木工は、2023年5月のG7広島サミットの円卓や首脳陣が座っている椅子を作成しました。

この記事へとたどり着いた方は、すでにマルニ木工のHIROSHIMA(ヒロシマ)アームチェアをご存じのことと思います。
ここで使われた椅子が、マルニ木工の名前を世界に知らしめたhiroshimaアームチェア。広島の名を冠した、これもまた名作の椅子です。
つまりマルニ木工は、
世界各国の首脳陣が集まる家具を一任されたメーカー
なのです。
日本でもトップクラスの職人が多数在籍し、一流の家具を数多く送り出しています。
私も仕事柄、数多くの家具を見ています。北欧家具のつくりは素晴らしいですが、こと職人の腕は日本人のほうが素晴らしいと感じます。
特に木材加工においては、日本の職人が世界一だと思います。つまりマルニ木工は世界でもトップクラスの木工技術があると言えます。
ハイブリッドなマルニ木工
さらに、マルニ木工はどこよりも機械化を目指したメーカーです。
職人と機械化とは、相反するものだと思われるかもしれませんが、実はプロセスを最大限に効率化した、ハイブリッドなメーカーなのです。
すなわち
機械で出来ることは機械に。人の手でしかできないことは人の手で。
ということ。
これを実現したいと考えているメーカーは多いと思いますが、マルニ木工ほどハイブリッド化できているところを私は知りません。
機械化すればするほど価格や品質、流通量は安定しますが、商品としての魅力は薄れていきます。対して、手作業化すればするほど、商品としての個性が際立ちますが、品質が安定せず価格も高額になってしまう。

今回の例で言うと、椅子を作るすべての作業を手作業でしたらどうなるのか?ということ。
良い木材を使い、一流の職人が1か月かけて椅子を1脚仕上げる…こんなことをしてしまうと、おそらく私たちの購入する段階で1脚100万円を超える価格になるでしょう。実際にこういったメーカーも世界にはたくさんあります。
マルニ木工の商品は、一般的に見て高い部類であると思います。しかし、
世界諸国の椅子よりもはるかに品質が高く、価格以上の価値がある
と、自信を持っておすすめできます。
皆様にはぜひ、このことを強く伝えたいです。

工業化することも、しないこともどちらも良いことがありますが、それらの利点をいいとこ取りしたのがマルニ木工のものづくりなのです。
マルニ木工の魅力は
品質に妥協しないけれど、商品の魅力にもけして手を抜かない
こと。
職人の腕だけに甘んじず、機械化できることは機械化を図る。これは、実に日本的なものづくりの極みです。
takoはヒロシマを超える椅子
上記の通り、hirosimaは2008年にデザインされ、アップルコンピュータ本社へと数千脚納入された日本を代表する名作チェアです。
アップルのモノ選びは非常に注目されているため、ヒロシマも当時一躍脚光を浴びました。
HIROSHIMAは国内でも名実ともに最高峰の椅子です。その椅子を超えることは並大抵のことではありません。事実、深澤さんの作品集「Naoto Fukasawa: Embodiment」の表紙にはHIROSHIMAアームチェアが使われています。
数々の名作を生み出す深澤さんが自身の作品集の表紙に選んだこと、これは深澤さんのデザインの自信の現れでもあり、マルニ木工の生み出したクオリティに対する信頼でもあります。
余談ですが、椅子のデザインは工業デザイナーにとってかなり難易度が高いです。特に、初めてデザインする椅子はかなり難しい。
椅子は
- 身体を支えなければならない『強度』
- 調度としての『美しさ』
- 道具としての『使い勝手』
これらを全て満たさなくてはならないのです。
しかも、デザイナーのキャリアを左右する。1脚目の椅子に失敗してしまうと、家具のデザインを仕事にするのが難しくなってしまう可能性もある。
名作が生まれるには、名作が生まれるまでの悲喜こもごもや壮大なストーリーがあるんですね。
takoの開発に当たってはマルニ側からデザイナーの深澤さんへ「HIROSHIMAアームチェアを超える椅子を作りたい」という依頼があったようです。
デザイナーは何を考えていたのか
デザイナーは深澤直人(ふかざわなおと)さんという方です。日本の工業デザインを牽引する、プロダクト界のトップデザイナーです。
これまでに残した有名なデザインで言うと、無印良品の換気扇型CDプレイヤーや、auの携帯電話「infobar」、プラスマイナスゼロの加湿器など。
深澤さんは、「スーパーノーマル」という哲学を持っていて、言い換えれば
すごく良い、ふつう
ということ。
普通を逸脱せず、いい塩梅の普通を目指す。これが深澤さんの哲学です。深沢さんは著書の『ふつう』の中でこんなことを語っていました。
いつも「ちょっといいふつう」をつくりたいと思っている。「ちょっといいふつう」が「ふつう」になるまでには少し時間がかかる。でもそれが「ふつう」になったらまた「ちょっといいふつう」をつくればいい。
深澤直人 著 「ふつう」より引用させていただきました (出版社:D&DEPARTMENT PROJECT)
デザインは奇抜なものではなく、生活に寄り添った「ふつう」のものであるべきではないか。深澤さんは著書や対談の中で幾度となくそれを語っています。
昨今の過度なデザインに疑問を持っている方は、ぜひこの本を読んでみてほしいです。
デザイナーのブレイクスルー
私は以前から深澤さんのデザインに関心があり、この「スーパーノーマル」の考え方についても知っていました。だからこそtakoを始めて見たとき、これが『ふつう』のデザイン?と感じました。
彫刻的なデザインのtakoは、無印良品の商品のようにシンプルで主張しないものではなく、空間を演出する一つのオブジェクトのようだと感じたのです。

しかし実はそれには経緯があり、深澤さんはマルニ木工の90周年のタイミングで同社から「HIROSHIMAを超える椅子」を依頼されます。
その依頼への深澤さんの回答は
『彫刻家としての椅子を作っていいですか?』
だったのです。深澤さんはこれまで、スーパーノーマルを貫いてきたデザイナー。その深澤さんが新たな切り口でデザインする…。これはインテリアデザイン界の大きな出来事だった、と私は思います。
デザイナーの深澤直人さんはマルニ木工の山中社長との対談の中で「彫刻のような椅子を作りたい」と語っていたことが、私にはそとても意外でした。
●彫刻の画像

深澤直人と言えば「ふつう」をデザインの信条に掲げているデザイナー。その深澤さんが「彫刻をつくる?」と違和感を感じたことを覚えています。
思うに、深澤さんの頭にあったのはインテリアデザインのブレイクスルーだったのではないかと。
シンプルなデザインを良しとしてきた深澤さんの中に、デザイナーではなくアーティストとしての感性が育ち、アート作品のようなプロダクトが生まれたのだと私は感じました。
熟練のインテリアデザイナーが、芸術的な感性をもって椅子を作ったらどうなるか…そのアンサーがこのtakoなのではないでしょうか。
●海のタコの画像

業界のある先輩が言った言葉『デザイナーとアーティストは似ているようで違う。デザイナーはクライアントと向き合い、アーティストは自分自身と対話する』
深澤さんはデザイナーとして活動し、アーティストとして表現をしたのではないか、と。デザインを超えたブレイクスルーが生み出すものは、これまで時代になかった製品ではないでしょうか。
絶対に名作に決まってます。
Takoはオーク、ウォールナットどっちがおすすめ?
ここからは、より具体的な商品の話をしていきますね。
私はウォールナットを購入
結論から言うと、私はウォールナットを購入しました。これは、懇意にしているインテリア関係の友人が言っていたのですが、2020年当時のTakoのカタログにはオークのヴィジュアル写真がなく、ウォールナットしか画像がなかったとのことでした。
深澤さんは、次のようなコメントを残しています。
曲木ではなく三次元的な自由曲線を量産の木の椅子に使いたかった。手作りの一品加工はできても量産ができないかたちを無垢の木で実現させたのがこの椅子である。ワインとか白いテーブルクロスが似合いそうな椅子が最初に思い浮かんだ。
深澤さんのイメージでは、ワインが似合うのはオークよりもウォールナットのイメージだったんでしょうね。確かに、赤ワインだったらウォールナットかな、と私も思います。
そんなストーリーを聞いて、私はウォールナットを購入しました。
また、ウォールナットにも塗装色がありますが、私がおすすめするのははCA-0(ナチュラルブラウン)塗装です。

ウォールナットは木材の特性上、濃い部分と薄い部分が混在します。その、薄い部分を濃い部分に合わせて捕色したのがCA-0塗装(ナチュラルブラウン)です。

他に、ライトブラウン(WB-1)という塗装もありますが、これは全体にブラウン色を重ねる塗装のため、ウォールナットの本来の色味よりも濃くなります。
基本的にはお好みで良いかと思いますが、インテリアコーディネーターの立場で言わせていただくと、基本的にはCA-0塗装(ナチュラルブラウン)で、ウェンジなどのかなり濃いブラウン色のばあ委は
オークのほうがインテリアには合わせやすい
しかし、どちらも実物を見てみての感想としては、どちらかと言うと合わせやすいのはオークかなと感じました。
ウォールナットは色が濃いため高級感が出るものの、部屋での存在感が強くなりがちです。対してオークは柔らかなカラーなのでお部屋に置いても圧迫感が少ないです。

インテリア全般に言えることですが、お部屋では薄い色のほうが圧迫感が出にくいため、合わせやすさを取るのであれば薄いカラーを中心に部屋を構成するのがおすすめです。
また、北欧のインテリアや和モダンなどもライトカラーの木材を組み合わせることが多いため、オークのほうが合いやすいシーンは多いかもしれません。
張座よりも板座がおすすめ
座面は
- 張座(はりざ)…クッションが敷きこまれているタイプ
- 板座(いたざ)…座面がそのまま木材になっているタイプ
の2種類ありますが、私は板座をおすすめします。
完全な私の好みの問題ですが、
板座のほうがより「彫刻感」があるから
です。ソリッドな感じでよりシャープに見えます。
また、張座の座面は傷んでしまいますので定期的な交換が必要ですが、板座は半永久的にそのまま使えます。(キズは付きますが、それはアジになると思うのです)
つまり、メンテナンスいらずで使えるのは板座のほう。同じ椅子をずっと使い続ける、と言う意味では板座が良いのではないかと私は感じます。
座り心地は当然張座のほうが良いですが、張座にするよりも私は置き型のクッションをおすすめします。こんな感じのやつですね。
【まとめ】Takoは名作になる椅子
私はインテリア業界に身を置いているため、これまでたくさんの椅子に座った経験があります。
例えばカールハンセン&サンのCH24(Yチェア)やイームズのシェルチェア、PP503(ザ・チェア)、飛騨産業のクレセント、ト―ネットのno209など、世界の名作チェアにも座りました。
●名作チェアがたくさんあるっぽい画像

名作チェアは一様にデザインが美しく、もし部屋に充分なスペースがあるのなら上記の名作椅子は全部ほしいくらい好きですが、その中から私はtakoを選びました。

takoはけして知名度が高いわけではなく、あまり知られていません。しかし、冒頭でも書いたとおり
絶対に名作になる椅子だ
と、感じたのです。
実は今も、takoに座りながらこのブログ記事を執筆しています。すでに目新しさはありません。部屋の一部になりました。そう、深澤さんがいうところの「ふつう」になったのです。

時折り見るその美しい後ろ姿や、アームを握ったときの何とも言えない高揚感。共に年月を過ごして行きたい、そう思える椅子を購入出来て私はとても満足しています。
takoはほんとうに素晴らしい椅子です。

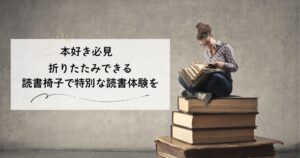


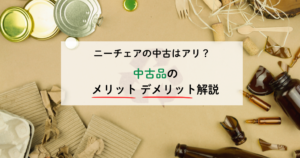
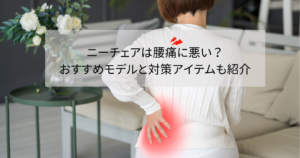


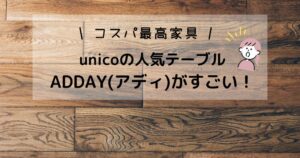
コメント